”結婚式の顔”とも言われるほど重要な存在になる「ペーパーアイテム」。
招待状や席次表・席札は必須だけど、プロフィールブックやメニュー表は作るべき?デザインはどう選ぶ?
――そんな疑問を持つ花嫁さんも多いはず。
そこで今回は、実例やデザインのアイディアを交えながら、ペーパーアイテムの選び方・作り方をまとめました。
こんな悩みをお持ちの方におすすめ!
- ペーパーアイテムを手作り or 外注で迷っている
- 招待状や席次表などの基本アイテムをどう選ぶか知りたい
- 実例や最新トレンドを参考にしたい
- プロフィールブックや席札のユニークなアイデアを探している
- できれば費用も抑えたいけど、手抜きには見せたくない
招待状|結婚式の“第一印象”を決める大切なアイテム

結婚式のペーパーアイテムの中でも、最初に準備するのが「招待状」。
ゲストの手元に最初に届くアイテムであり、結婚式の第一印象を左右する大切な存在です。
送る時期やマナーに気をつけながら、ふたりらしいデザインで準備しましょう。
送る時期とマナー
招待状は 結婚式の2~3か月前 に発送するのが一般的。
そのため、逆算すると
式の6か月前までには招待したいゲストのリストアップ、
3~4か月前にはデザイン・文面を決定 しておくと安心です。
- 出席の返信期限は、結婚式の1か月前の「大安」または「友引」の日
- 親族や上司には直接手渡し すると丁寧な印象に
- 封筒の宛名は毛筆や筆ペンで書くのがマナー
(ただし最近は外注印刷や美文字フォントを使う人も多い) - 句読点・忌み言葉は避けよう
💡最近のトレンド💡
最近では、WEB招待状を取り入れるカップルも増えています。
「返信が早い」「URLで簡単にシェアできる」などメリットも多いですが、
年配ゲストには紙の招待状を併用すると安心です。
デザイン選びのコツ
結婚式の招待状に必要なアイテムは、①招待状の本状 ②封筒 ③返信はがき ④会場案内図 ⑤付箋(各種お願い事を書く) ⑥二次会の案内状(あれば) ⑦切手(封筒と返信はがき用)など。
これらのデザインに悩んだ時は、「結婚式のテーマや会場の雰囲気」に合わせるのがおすすめ。
- クラシック婚(ホテル・格式高い会場など)
→ 格調高い厚紙や金箔・リボン加工 - ナチュラル婚 (ガーデン・レストラン・カジュアルウェディングなど)
→ 花柄やグリーン系・手書き風デザイン - 和婚(神社・和装中心の式)
→ 和紙や水引、着物柄の和モチーフ - リゾート婚 (沖縄・ハワイなど)
→ 水彩やブルー系、貝殻など海風なデザイン
封筒や付箋まで統一すると、全体の完成度がぐっと高まります。
また、ゲスト層や関係性に合わせて選ぶのも大切なポイント。
年配ゲストや親族が多い式なら、格式や上質さを感じるクラシックなデザイン。
友人中心のカジュアルな式であれば、トレンド感や自分たちらしさを表現できるデザインがおすすめです。
手作り vs 外注のメリット・デメリット
▼手作りのメリット
- デザインを自由にアレンジできる
- コストを抑えやすい(1通あたり数百円安くなることも)
- Canvaなどのテンプレートを使えばおしゃれに仕上がる
▼手作りのデメリット
- 印刷・カット・封入などにかなりの時間がかかる
- プリンタートラブルで想定外のストレスになることも
- 大量印刷が必要な場合は逆にコスト高になる場合も
▼外注のメリット
- プロに任せる安心感、クオリティが高い
- マナーに沿った文面・レイアウトを提案してもらえる
- 納期を守ればスケジュール管理が楽
▼外注のデメリット
- デザインがテンプレートに限られることもある
- 1通あたりのコストは手作りよりやや高め
- 修正や変更に時間がかかる場合がある
手作りは費用を抑えやすく自由度も高い反面、手間と時間がかかりやすいのがデメリット。
外注はコストは上がりますが、完成度が高く安心して任せられるのが魅力です。
| 費用 | クオリティ | 手間 | |
| 手作り | ◎ | ○ | △ |
| 外注 | △ | ◎ | ○ |
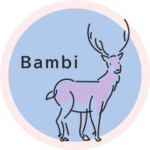
おすすめは「親族や上司には外注の紙招待状」「友人にはWEB招待状」という
ハイブリッド方式。時間もコストも節約できるよ!
【招待状】おすすめ実例
ナチュラル×おしゃれ:ブルー系基調、花柄でアクセント

シンプル×上品:グレーに金箔基調、封筒にも金箔で統一

オリジナル:好きなキャラクターを用いてデザイン

WEB招待状:テンプレートに写真を挿入できる

席次表|ゲストをつなぐ“関係性の地図”
ゲストがどこに座るかを示す「席次表」は、ゲスト同士の関係性を伝えるアイテムでもあります。
新郎新婦から見た配置順や、家族・職場・友人などのつながりが一目でわかるため、
ゲストが安心して着席できる大切なペーパーアイテムです。
最近では「席次表+プロフィールブック+メニュー表」を一冊にまとめた冊子型タイプも人気。
紙の量を減らしつつ統一感を出せるので、スマートな印象に仕上がります。
席次表の手配方法 手作り?外注?
席次表の準備には、主に次の4つの方法があります。
それぞれの特徴を理解して、自分たちのスケジュールやこだわりに合った方法を選びましょう。
① 会場にすべて依頼する
一番手間がかからず、打ち合わせの中でまとめて発注できる方法。
会場の雰囲気に合ったデザインを提案してもらえる安心感があります。
ただし、費用はやや高めになる傾向があります。
② 外部業者に依頼する
デザインの自由度が高く、価格も会場より抑えやすいのがメリット。
ネットショップやデザインスタジオなど、さまざまなテンプレートが選べます。
ただし、納期や校正の確認は自分で管理する必要があります。
③ すべて手作りする
テンプレートを使ってデザインから印刷まですべて自作する方法。
自由度は抜群ですが、印刷や裁断などの作業が多く時間と手間がかかる点には注意。
少人数婚やDIY好きの花嫁におすすめです。
④ デザインのみ手作りして、印刷を外注する
「自分でデザインしたいけど、印刷はプロに任せたい」人にぴったり。
Canvaなどの無料ツールでデザインを作り、印刷は業者にお願いすることで、
手間とクオリティのバランスが取りやすいのが魅力です。
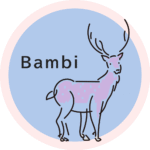
💡Bambiの実例紹介💡
席次表・プロフィールブック・メニュー表を一冊にまとめた”冊子型タイプ”にした!Canvaでデザインし、外注で印刷をお願いしたよ
また、受付横にはB2サイズの席次表を飾るアレンジも。
フォトフレームを自分で準備して、コンビニで印刷!
作るときの注意点(配置のルール、肩書きの書き方)
席次表は式の2~3か月前には「手作りにするか・外注にするか」、「デザインはどうするか」などを決め始めましょう
1か月前には、ゲストの配席やレイアウトを確定し、印刷の準備に入っておくと安心です。
配席の基本のルールとしては「新郎新婦に近い席=上座」となり、
上司や親族の目上の方を前方に、友人や同僚は後方に配置するのが一般的です。
肩書きの記載も意外と見られるポイント。
会社関係なら「株式会社◯◯ 代表取締役」のように正式名称を書くと丁寧で、
親族には「新郎伯父」「新婦従妹」といった表記を入れると分かりやすくなります。
【席次表】おすすめ実例
- 冊子型:
プロフィールやメニューも一緒にまとめられるタイプ。情報量が多い式にぴったり。 - エスコートカード型:
必要最低限の情報をまとめたシンプルなデザイン。トレンドで少人数婚に合う。 - ボード型/ディスプレイ型:
受付や会場入口に大きく掲示するスタイル。装飾も兼ねて写真映えするので海外でも人気。
冊子型:席次表・メニュー表・プロフィールブックを一冊に

エスコートカード型:思い出写真のチェキに席と名前を書いて

席札|ゲスト一人ひとりへの小さな“おもてなし”

席札は、ゲスト一人ひとりの席を示すアイテム。
披露宴会場で「どこに座るか」をすぐに分かってもらえるようにするための、欠かせないペーパーアイテムです。
最近は名前だけでなく、メッセージを添えたり、ギフトと兼ねたりするデザインも人気。
ゲストに感謝を伝える“小さなサプライズ”として取り入れる人も増えています。
席札の選び方とスタイル別アイデア
席札は、ゲスト一人ひとりの名前が入る“特別感”のあるアイテム。
素材やデザイン次第で、テーブルコーディネート全体の印象も大きく変わります。
選ぶときは、式のテーマや装飾との統一感を意識するのがおすすめ。
ナチュラルな雰囲気ならクラフト紙や木製、
上品な雰囲気ならアクリルやミラー素材など、
“空間になじむ席札”を意識するとまとまりが出ます。
また最近は、「席札+α」で工夫する花嫁さんも増えています。
たとえば──
- 席札に手書きメッセージを添えて感謝を伝える
- 席札をキャンドルやミラーに仕立てて、そのままプチギフトとして渡す
- 席札をブローチ風にして、写真撮影時のドレスコードアイテムとして楽しんでもらう
ちょっとした工夫で、席札が“記念品”に変わります。
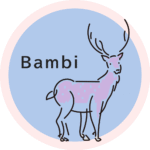
💡Bambiの実例紹介💡
手のひらサイズのミラーを購入して、そこに名前を手書きしました。
「実用的でうれしい!」とたくさんのゲストが持ち帰ってくれて、今でも使ってくれているそうです
【席札】おすすめ実例
席札×お菓子

席札×手紙

席札×ミラー

プロフィールブック|“ふたりのこと”を知ってもらう1冊

プロフィールブックは、新郎新婦について知ってもらうためのペーパーアイテム。
いわば「ふたりのことをもっと知ってもらうためのパンフレット」です。
手作りで世界観を出すのも良いですし、デザイン重視で外注するのもおすすめです。
どんな内容を入れる?
定番で入れたい内容
- 新郎新婦のプロフィール
生年月日や出身地、職業などの基本情報に加えて、お互いの第一印象や好きなところを書くと温かみが出ます。 - ふたりのなれそめ・プロポーズエピソード
写真やイラスト付きで紹介すると、ゲストの会話も弾みます。 - 当日のスケジュール・プログラム
披露宴の流れがわかると、ゲストも安心して参加できます。 - 前撮り写真
和装・洋装・ロケーションフォトなどを掲載すると、おふたりの雰囲気をゲストにしっかりと伝えられます。
入れると喜ばれるアイディア
- 家族・友人へのメッセージ
直接言えない感謝の言葉を紙面で伝えると感動されやすいポイント。 - 思い出フォトギャラリー
旅行、日常ショットなどをミニアルバム風に。 - ふたりの好きなもの紹介
趣味・映画・カフェなど、共通の話題を見つけてもらえるきっかけに。
ゲストが待ち時間に読んで楽しめる工夫をすると、式全体の雰囲気も和やかになります。
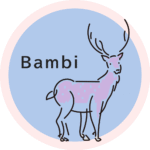
💡Bambiの実例紹介💡
定番のなれそめ紹介は少し照れくさかったので、質問形式でふたりの個性を紹介しました。
・好きなサウナは?
・家系ラーメンの注文方法は?(麵の硬さ・スープの濃さ・油の量)
・二人のMBTIタイプは?
・お風呂の時、体はどこから洗う?
見やすく・伝わるデザインのコツ
プロフィールブックは“情報量が多い”アイテムだからこそ、見やすさと統一感が大切。
- ページごとにテーマカラーを統一する
- 文字サイズやフォントをそろえる
- 写真は見開きに1~2枚までにして余白を活かす
- 見出しや区切りにアイコンや罫線を使うとすっきり
デザインを迷ったときは、席次表や招待状と同じトーンで作ると統一感が出ておすすめです。
今どきのプロフィールブック事情
最近は、紙冊子にこだわらずデジタル化するカップルも増えています。
受付やテーブルに置いたQRコードからアクセスできる「Webプロフィールブック」なら、
写真や動画を入れたり、リンクでエピソードを詳しく紹介したりと自由度が高め。
印刷代もカットでき、準備や修正もしやすいのが魅力です。
また、席次表+メニュー表+プロフィールを一冊にまとめる“まとめ型”スタイルも人気。
どの形式でも大切なのは、ゲストが見やすく、ふたりらしさが伝わること。
紙・デジタルのどちらを選ぶ場合でも、内容とデザインのバランスを意識して作るのがポイントです。
まとめ:ふたりらしさを形にできるのがペーパーアイテムの魅力
ペーパーアイテムは、ゲストの手に一番近い“おもてなしの形”。
デザインや言葉のひとつひとつに、ふたりの世界観や感謝の気持ちが表れます。
手作りでも外注でも、**大切なのは「誰にどう伝えたいか」**という気持ち。
紙にこだわるのも、デジタルでスマートにまとめるのも正解です。
ゲストが思わず笑顔になるような、自分たちらしいペーパーアイテムを楽しみながら作ってみてください。
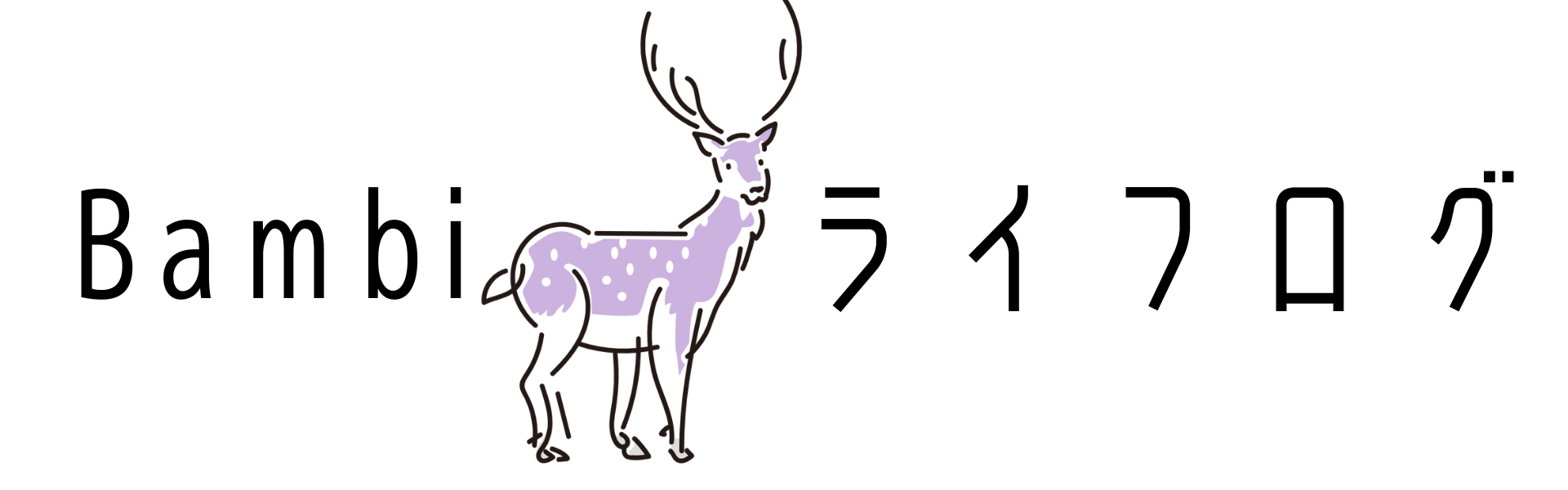
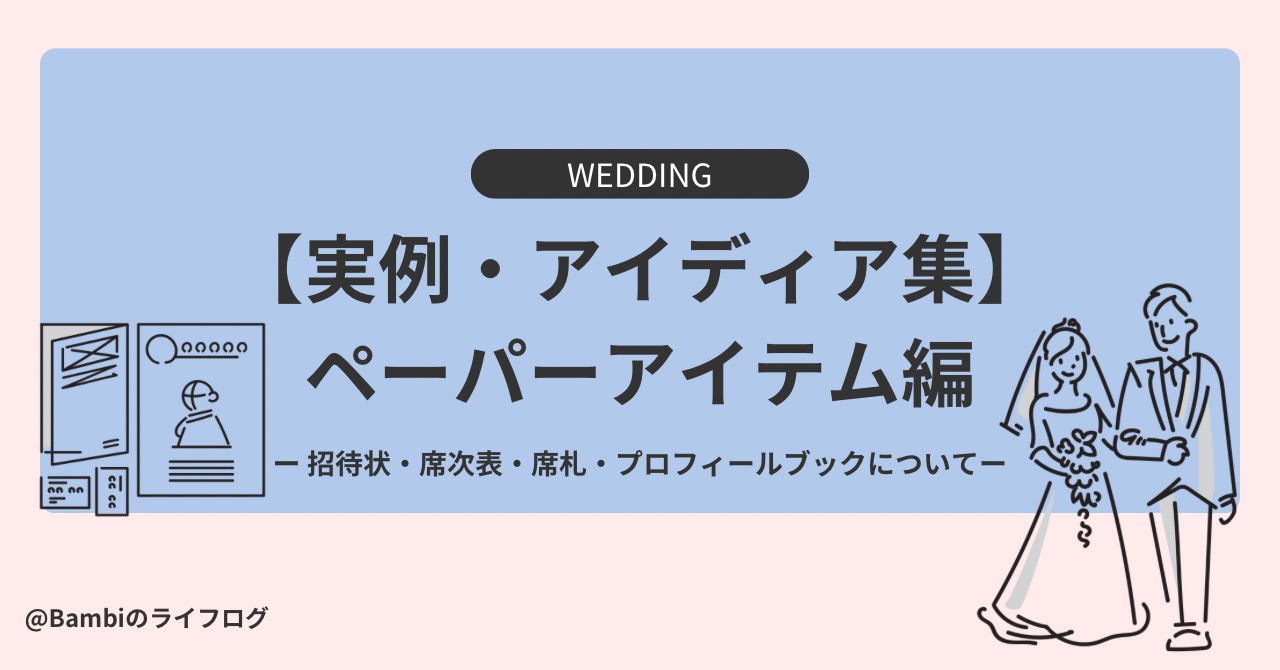
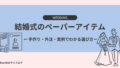
コメント